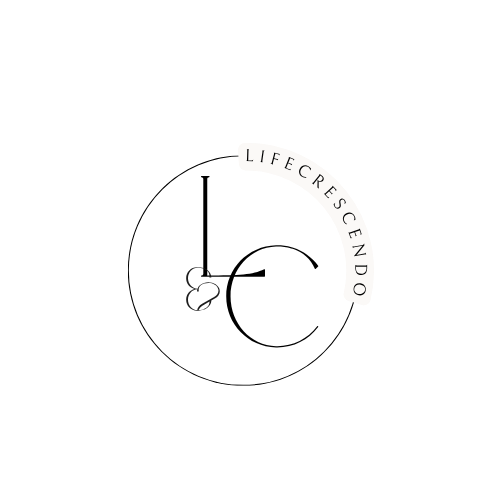【はじめに】なぜ、同じ病気でも“治る子”と“治らない子”がいるのか
はじめまして。小森こどもクリニック院長の小森広嗣です。
私はこれまで、小児病院などで長年、小児外科医として子どもたちの治療に携わってきました。
「小児外科医」というと、手術のイメージが強いかもしれません。しかし、私たちの仕事にはもう一つ、非常に重要な柱があります。それは、生まれつきお腹(腸)にハンディキャップを持って生まれたお子さんたちが、退院後も健やかに成長・発達していけるよう、長期的にサポートすることです。
手術が成功しても、その後の人生を力強く生きていくためには、日々の「栄養管理」が何よりも重要になります。腸の状態を熟知し、栄養をいかに吸収させ、成長の糧とするか。その一点を突き詰める中で、私たちは「腸と栄養のプロフェッショナル」でもあるのです。
そうした経験の中で、私はずっと一つの大きな疑問を抱き続けてきました。
それは、「なぜ、子どもたちの“治る力”にこれほど大きな個人差があるのだろうか?」ということです。
例えば、同じ風邪と診断しても、数日で元気に走り回る子がいる一方で、咳や鼻水がずっと長引き、何度もぶり返してしまう子がいる。同じ手術をしても、驚くほど順調に回復していく子と、なかなか傷の治りが悪く、体力が戻らない子がいる。あるいは、季節の変わり目に必ず体調を崩す子と、一年中ほとんど風邪をひかない子がいる。
この違いを、私たちはこれまで「個性」や「体質」、あるいは「遺伝」といった言葉で、ある意味では片付けてきました。しかし、本当にそれだけなのでしょうか。目の前で苦しんでいる子どもたちを前に、その言葉だけで思考を止めてしまって良いのだろうか。その葛藤が、常に私の中にありました。
そして、その答えを探し求め、国内外の様々な医学研究や臨床経験を重ねる中でたどり着いた一つの確信。それが、日々の食事によって作られる『栄養』という、目には見えない“土台”の重要性です。
この記事は、単なる健康情報ではありません。かつての私と同じように、お子さんの体調に悩み、「なぜだろう」と心を痛めているLifeCrescendo読者の皆さんと共に、「治る力の個体差」という謎を解き明かすための、一つの旅です。
私たちのクリニックそしてLifeCrescendo哲学が最も大切にしている理念は、健全な「体」という土台なくして、豊かな「心」や「道徳」は育たない、という考え方です。
しっかりとした根がなければ美しい花が咲かないように、頑丈な土台がなければ立派な家が建たないように。私たちの心や思考、そして他者を思いやる気持ちもまた、病気から回復する力、すなわち生命力の土台の上でこそ、まっすぐに育まれていく。
この記事では、あえてその最も根源的である「栄養学」という切り口に特化します。最新の科学的知見に基づき、「昔」と「今」の食事を比較分析することで、お子さん一人ひとりが持つ「治る力」を最大限に引き出すための、現代に最適化された食事戦略を、皆さんと一緒に見つけていきたいと思います。
第1章:【大前提】すべての土台となる「栄養」そのものの変化
1-1. 総論:現代の食卓は豊かになった。しかし、体を治す“部品”は満たされているか?
現代は飽食の時代です。しかしその一方で、「カロリーは足りているのに、体を修復し、ウイルスと戦うための“部品”が足りていない」という、新しいタイプの栄養失調、いわば「質的栄養失調」に陥っている子が少なくありません。
車に例えるなら、ガソリン(カロリー)は満タンでも、エンジンオイルや精密な電子回路を動かすための特殊な金属(ビタミン・ミネラル・良質な脂質)が足りていない状態。これでは、車は本来の性能を発揮できず、故障(=病気)からの回復も遅れてしまいます。特に、爆発的なスピードで成長し、常に体を新陳代謝させている子どもたちにとって、この“部品”の不足は、「治る力」に直接影響します。
1-2. データで見る光と影①:脳と細胞膜の材料となるn-3系脂肪酸(魚油)の決定的な不足
体を構成する約37兆個の細胞は、すべて細胞膜という油の膜で覆われています。この膜の質が、細胞の働き、ひいては免疫細胞の働きを左右します。青魚に多いn-3(オメガスリー)系脂肪酸は、この細胞膜をしなやかに保ち、炎症を適切にコントロールする重要な“部品”です。しかし、現代の食事ではこのn-3系脂肪酸が著しく不足し、炎症を促進しやすいn-6系脂肪酸に偏りがちです。このバランスの崩れが、アレルギー反応の強さや、炎症の治まりにくさの一因となっている可能性があります。
1-3. データで見る光と影②:免疫の司令塔ビタミンD、精神安定剤カルシウムの慢性的な欠乏
ビタミンDは、免疫機能の司令塔として、侵入してきた敵と戦うべきか、あるいは攻撃を収めるべきかを的確に判断する上で不可欠な“部品”です。ビタミンDが不足すると、この司令塔がうまく機能せず、感染症にかかりやすくなったり、アレルギー反応が過剰になったりします。屋外活動が減った現代では、ほとんどの人が不足状態にあると言っても過言ではありません。また、カルシウムは神経の興奮を鎮める働きがあり、病気の時に乱れがちな自律神経のバランスを整える上でも重要です。
1-4. 新たな課題「超加工食品(UPF)」:手軽さと引き換えに、“治る力”の土台を蝕む可能性
スナック菓子やカップ麺、清涼飲料水などの「超加工食品(UPF)」は、体を治すために必要なビタミンやミネラルが削ぎ落されているだけでなく、多量の糖質が血糖値を乱高下させ、体の回復に必要なエネルギー供給を不安定にします。また、腸内環境を悪化させる一因ともなり、免疫力の土台そのものを静かに、しかし確実に蝕んでしまう可能性があるのです。
第2章:【からだ(器)編】病気に負けない“器”の変遷
2-1. 指標①「成長」:体は大きくなった。しかし、生命のスタート地点(出生体重)では懸念も
戦後から現代にかけて、日本の子どもたちの平均身長が著しく伸びたことは、誰もが知る事実です。これは間違いなく、安定した食料供給による栄養改善の賜物であり、現代が手に入れた大きな恩恵の一つと言えるでしょう。
しかしその一方で、私たちは生命のまさに“スタート地点”において、見過ごすことのできない課題に直面しています。それは、赤ちゃんの「出生体重」が、この30~40年ほど長期的に減少傾向にあるという事実です。
「少し小さく生まれても、その後大きく育てば問題ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、近年の研究では、お母さんのお腹の中にいる胎児期の栄養状態が、その子の一生涯の健康を左右する「DOHaD(ドゥーハッド)学説」という考え方が常識となりつつあります。
これは、胎内で栄養不足の状態を経験した赤ちゃんは、エネルギーを効率的に溜め込もうとする“省エネ体質”のスイッチが入った状態で生まれてくる、というものです。その子が成長し、飽食の時代である現代社会を生きると、その省エネ体質が裏目に出てしまい、将来的に肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病を発症しやすくなる可能性があるのです。
お母さん自身の無理なダイエットや、妊娠中の栄養不足が、意図せずして子どもの未来の健康リスクを高めてしまうかもしれない。これは、私たち現代人が真摯に受け止めるべき課題だと考えています。
2-2. 指標②「骨と筋肉」:強い身体は、病気からの“回復力”そのもの
「遊び」の中で自然と育まれる強い骨と筋肉は、困難に立ち向かう心の強さの源泉となるだけでなく、病気からの“回復力”そのものです。特に筋肉は、体を動かすエンジンであると同時に、体を構成するタンパク質の最大の貯蔵庫です。高熱を出したり、大きな怪我をしたりした時、私たちの体は筋肉を分解してアミノ酸を取り出し、免疫細胞や傷を治すための材料として使います。つまり、筋肉量が十分にあることは、いざという時のための「回復力の貯金」を持っていることと同じなのです。
2-3.【比喩で解説】身体は「家づくり」:人生の最も重要な時期に行うべき「基礎工事」とは何か
ここで、私たちの体づくりを「家づくり」に例えてみたいと思います。
お母さんのお腹の中にいる胎児期から、骨格や内臓が完成する思春期まで。この期間は、家の土台や柱、梁といった最も重要な構造部分を作り上げる「基礎工事」の時期にあたります。
この基礎工事の時期に、良質な材料(栄養)が十分に供給され、適切な刺激(運動)が加わることで、頑丈でびくともしない家が建ちます。この大切な時期に、親が子どものためにできるサポートは計り知れません。
そして、成人期以降は、その家を大切に維持していく「メンテナンス」の時期に入ります。基礎がしっかりしていれば、多少の嵐が来ても家はびくともしませんし、メンテナンスも比較的楽に進みます。
しかし、もし基礎工事が不十分だったらどうでしょうか。どんなに立派で高価な家具(教育や知識)を室内に置いたとしても、家そのものが傾いてしまっては、元も子もありません。
私たちは、子どもたちに健やかな人生を歩んでほしいと願うからこそ、何よりもまず、この「基礎工事」の重要性をお伝えしたいのです。
第3章:【こころと免疫(機能)編】“治る力”の個体差を生む、見えない土台の真実
3-1. 総論:「かかりやすさ」や「治りにくさ」は、体からの“土台の脆弱性”を知らせるサイン
なぜ、同じ環境にいても風邪をひきやすい子とひきにくい子がいるのか。その答えの多くは、この「目に見えない機能」、すなわち免疫システムのバランスに隠されています。それは単なる体質の問題ではなく、栄養という土台によって後天的に育むことができる機能なのです。
3-2. 「心の健康」と栄養の直結:病気の時の“機嫌”も“食べたもの”で変わる
病気になるとき、子どもは不安になったり、機嫌が悪くなったりしがちです。実はこれも栄養状態と無関係ではありません。血糖値が安定していれば、体調が悪くても比較的穏やかに過ごせますが、血糖値が乱高下していると、不快感に耐えられず、ぐずりや癇癪がひどくなることがあります。また、腸内環境が良いと、病原体に対する抵抗力が高いだけでなく、心の安定にも繋がることがわかっています。
3-3. 「免疫システム」の誤作動: “治る力”の差は、免疫バランスの差
優れた免疫システムとは、ウイルスや細菌と戦う“攻撃力”と、むやみに暴走しない“制御力”のバランスが取れた状態を指します。まさにこの免疫バランスの差が、風邪のひきやすさや、病気の治り方の違いに直結してくるのです。
このバランスを整える鍵は、過度な清潔志向を見直し、腸内細菌をはじめとする多様な微生物と共生すること。そして、その腸内細菌を育むための食事(発酵食品や食物繊維)を摂ることです。この見えない土台を育むことが、病気に負けない体づくりの本質と言えるでしょう。
第4章:【実践ガイド】家庭で育む「治る力」の土台 ― 栄養学的アプローチ
4-1. ゴール設定:完璧でなくていい。家庭でできることから始めよう
ここからお話しするのは、「治る力」の土台を、ご家庭で育むための具体的な方法です。決して難しいことや、完璧を求めるものではありません。「これならできそう」と思えるものから、ぜひ試してみてください。
4-2. 日々の食事で実践する「7つの戦略」
- 戦略1:魚の力を取り戻す (→集中力と思考力の土台)
現代の食事で最も不足しているn-3系脂肪酸を補うため、週に2~3回は食卓に魚、特にアジ、サバ、イワシ、サンマなどの青魚を取り入れましょう。調理が大変であれば、サバやイワシの缶詰(水煮や味噌煮がおすすめです)を常備しておくと非常に便利です。お味噌汁に入れたり、野菜と和えたりするだけで、立派な一品になります。 - 戦略2:骨と心を強くする (→精神的な安定性の土台)
カルシウムとビタミンDは、常にセットで考えることが大切です。カルシウムは、牛乳やヨーグルトなどの乳製品だけに頼らず、小魚、豆腐や納豆などの大豆製品、小松菜や水菜などの青菜、ひじきなど、様々な食品から摂ることを意識しましょう。ビタミンDは、サケやサンマといった魚類、そしてキノコ類に多く含まれています。 - 戦略3:感情の波を穏やかにする (→自己コントロール能力の土台)
血糖値のジェットコースターを防ぐ最も簡単な方法は「食べる順番」を工夫することです。食事の最初に、お味噌汁やスープ、野菜のおかず(食物繊維)から食べ始め、次に肉や魚(タンパク質・脂質)、そして最後にご飯やパン(炭水化物)を食べるように意識するだけで、血糖値の上昇はかなり緩やかになります。 - 戦略4:腸を育てる (→ストレス耐性と免疫バランスの土台)
元気な腸内環境のためには、「善玉菌そのもの(プロバイオティクス)」と、「腸内で善玉菌のエサとなるもの(プレバイオティクス)」の両方が必要です。味噌、納豆、醤油、ぬか漬け、ヨーグルトといった発酵食品と、海藻、きのこ、根菜、豆類、全粒穀物などに豊富な食物繊維を、毎日少しずつでも食卓に取り入れましょう。 - 戦略5:賢く減塩する (→生涯にわたる健康の土台)
日本の伝統的な食事は塩分が高くなりがちです。しかし、これも工夫次第で改善できます。昆布や鰹節でしっかりと出汁をとることで、味噌や醤油の量を減らしても、料理の満足感は格段に上がります。また、お味噌汁は野菜やきのこ、海藻などをたっぷり入れた具沢山にすることで、一杯あたりの汁の量を減らし、栄養価も高めることができます。 - 戦略6:超加工食品(UPF)と賢く距離をとる (→味覚と心身を守る土台)
UPFを日常生活から完全に排除するのは、現実的ではないかもしれません。大切なのは、依存しすぎず、賢く付き合うことです。まずは「おやつのスナック菓子を、おにぎりやふかし芋、果物に変えてみる」「ジュースではなく、お茶か水を選ぶ」といった、簡単な「置き換え」から始めてみてはいかがでしょうか。 - 戦略7. 未来の世代を育む (→次世代の心と体の土台)
これから新しい命を育むことを考えている方、そして妊娠中のお母さんには、ご自身の体とお腹の赤ちゃんのために、特に葉酸、鉄、そしてDHAやビタミンDを意識して摂取していただきたいと思います。これらは、赤ちゃんの脳や神経、骨格が作られる上で、特に重要な役割を果たす栄養素です。
4-3. 補足:食事に加え、運動・日光・睡眠が土台をさらに強固にする
これまで栄養の話に特化してきましたが、私たちの体は食事だけでできているわけではありません。
適度な運動は骨や筋肉を育て、脳への血流を増やします。
日光を浴びることは、体内のビタミンD合成に不可欠です。
そして、質の高い睡眠は、日中に受けた心身のダメージを修復し、記憶を定着させ、成長ホルモンを分泌させるための、何にも代えがたい時間です。
良い食事が、運動・日光・睡眠の効果を最大限に引き出し、またその逆も然り。これらが一体となって、初めて強固な土台が完成するのです。
【結論】「治る力の差」は、運命ではない
1. LifeCrescendo読者の皆さんへ
この記事の出発点であった「なぜ、同じ病気でも“治る子”と“治らない子”がいるのか?」という問い。その答えは、決して「個性」や「体質」といった言葉だけで終わるものではない、ということがお分かりいただけたかと思います。
その差の多くは、日々の食事によって育まれる栄養という土台の差であり、それはつまり、私たちの選択によって後天的に育むことができるものなのです。
2. 土台作りは、ゴールではなくスタート
もちろん、栄養がすべてではありません。私たちがここまで熱心にお話ししてきた「栄養」は、あくまで土台です。そして、土台作りは、ゴールではなく、すべての始まりにすぎません。
その頑丈な土台の上に、どのような素晴らしい「心」や「道徳」という家を建てるかは、ひとえにご家庭での愛情あるコミュニケーションや、地域社会での多様な人との関わり、そして様々な学びの機会にかかっています。
3. 最後に
子育ては、喜びも大きいですが、時に孤独で、不安になるものです。お子さんの繰り返す体調不良や、なかなか治らない症状に、「なぜうちの子だけ…」と悩んだときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。
この記事でお伝えしたかったのは、体という土台を整えることが、豊かな心と精神を育む揺るぎない第一歩であるということです。これは、人を心身に分断せず、統合的に捉える「全人格的アプローチ」の考え方にも通じる、医学的にも非常に重要な視点だと、私は考えています。
この記事が、LifeCrescendo読者の皆さんの日々の食生活を見つめ直し、お子さんの持つ本来の力を引き出すための一助となれば、これに勝る喜びはありません。
長い文章を最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
読者の皆さんからよくいただくご質問(Q&A)
この記事の内容を踏まえ、外来診療やこれまでの情報発信でよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 忙しくて、なかなか食事に手をかけられません。サプリメントを使っても良いですか?
A1. もちろん、栄養補助食品(サプリメント)を賢く利用するのは一つの有効な手段です。特にビタミンDや、魚を食べる機会が少ない場合のDHA/EPAなどは、サプリメントでの補充が効果的な場合があります。
ただし、大前提として「食事こそが基本」であることは忘れないでください。サプリメントはあくまで“補助”です。食事からは、ビタミンやミネラルだけでなく、食物繊維や、まだ科学的に解明されていない様々な機能性成分(ファイトケミカルなど)を複合的に摂取できます。
まずはこの記事でご紹介した「サバ缶をお味噌汁に入れる」「おやつをおにぎりに変える」といった簡単なことから始めていただき、その上でどうしても補いきれない部分をサプリメントで補う、という考え方が理想的です。
Q2. うちの子はアレルギーが多く、食べさせられるものが限られています。どうすれば良いですか?
A2. 食物アレルギーをお持ちのお子さんの食事管理は、本当に大変なこととお察しします。除去が必要な食品がある場合、代替食品をうまく使って栄養バランスを整えることが非常に重要になります。
例えば、乳製品アレルギーでカルシウムが不足しがちな場合は、小魚や青菜、大豆製品、ゴマなどを意識的に取り入れます。小麦アレルギーの場合は、米粉や玄米、イモ類などを主食の軸に据えます。
大切なのは、一人で悩まず、必ずかかりつけの医師や管理栄養士に相談することです。アレルギーの状態は一人ひとり異なりますので、専門家と一緒に、お子さんに合った安全で栄養価の高い食事プランを立てていきましょう。
Q3. どれくらいの期間続ければ、子どもの体質は変わってきますか?
A3. とても良い質問ですが、最もお答えするのが難しい質問でもあります。人の体が細胞レベルで入れ替わるには、少なくとも3ヶ月~半年はかかると言われています。まずは「3ヶ月」を一つの目安として、できる範囲で続けてみてください。
しかし、焦る必要はまったくありません。「風邪をひく回数が少し減ったかな?」「前より機嫌が良い時間が増えたかも」といった小さな変化に気づくことが大切です。食事改善は短期的な結果を求めるものではなく、お子さんの一生涯の健康という「家の基礎」を、毎日少しずつ作り上げていく、長期的なプロジェクトなのです。
この記事の執筆にあたり参考にした情報
本記事は、筆者の臨床経験に加え、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」、各種国民健康・栄養調査、国内外の栄養学・免疫学に関する学術論文など、信頼性の高い情報源に基づいて執筆しています。
著者プロフィール
小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)
慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は東京都国分寺市で「小森こどもクリニック」の院長として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。
当院では「体という土台の上に、心や道徳が育つ」という考えを大切に、日々の診療を行っています。この記事を通じて、一人でも多くのご家庭が、楽しく安心して子育てができる社会を創る一助となれば幸いです。