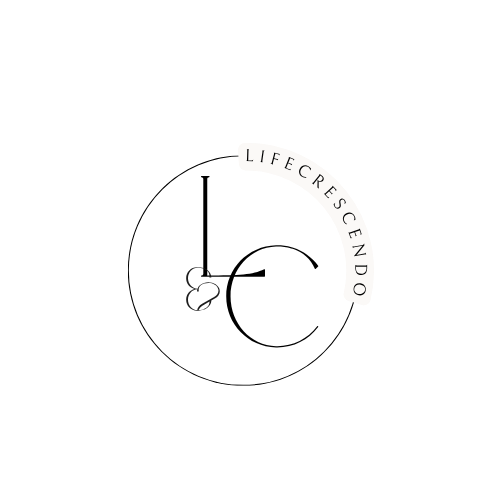こんにちは!
夫が小児科医、そして私は3人の子育てをしながら心と体のつながりをお伝えしている、ライフコーディネーターのちあきです。
スッキリしない朝を迎える、私。
学校で、急な「お腹いたい…」に悩む、息子。
実は私、物心ついた小学生の頃から、ずーっと頑固な便秘に悩んできました。一方で、我が家の長男は、どちらかというとお腹がゆるくなりやすいデリケートなタイプ。
「出ない」悩みと、「出すぎる」悩み。
全く正反対だから、「これはもう、体質や個性なんだろうな」と、長年そう思い込んでいたんです。
でも、タッチケアの学びの根底にある東洋医学、そして最近探求を始めた分子栄養学の世界に触れて、この二つの悩みが、実は「腸の消化・吸収する力が弱っている」という、同じ根っこで繋がっている可能性に気づかされました。
もしあなたが、ご自身やお子さんの尽きないお腹の悩みで心を痛めているなら、この記事がきっと、希望の光になるはずです。
実は同じ根っこ?「出ない悩み」と「出すぎる悩み」の意外な共通点
私が普段お伝えしているベビーマッサージやタッチケアは、東洋医学の知恵がベースになっています。その学びの中でまず驚いたのが、「便秘がちな人も、下痢をしやすい人も、どちらも『消化器官が弱い』という同じ仲間なんですよ」ということでした。
正反対に見えるのに、同じ!? まさに目からウロコでした。
そして、さらに学びを深めている分子栄養学の世界でも、これらの症状は「消化不良」のサインとして、やはり同じ括りで捉えられていたのです。
ここで、ご自身の生活を振り返る、ちょっとしたチェックリストを一つ。
□ 小麦製品(パン、パスタ、うどんなど)が大好きで、よく食べる
□ 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)を毎日摂るのが習慣だ
□ 花粉症やアトピーなど、何かしらのアレルギー体質である
□ 原因は分からないけれど、蕁麻疹が出やすい
□ ジャンクフードやスナック菓子を、つい食べてしまう
…いかがでしたか?
何を隠そう、私自身「乳製品大好き、アレルギーあり、チョコレートも大好き…」と、見事に当てはまってしまいました(苦笑)。
そして、頻便だった長男のことを思い返してみると…彼は赤ちゃんの頃、小麦と乳製品のアレルギーがあったんです。アレルギー反応が出なくなったので「もう大丈夫!」とすっかり安心していたのですが、西洋医学的にアレルギーを『克服』したとされても、彼の腸にとってはまだ、その食べ物を受け入れるのが少し負担だったのかもしれません。そのサインのように、今でも花粉症や肌荒れに悩まされています。
「もしかして、あの頃のアレルギーと、今のお腹の不調は繋がっている…?」
そう気づいた時、バラバラに見えていた悩みの点と点が、一本の線で繋がったような気がしました。
大丈夫、できることから始めよう。心と体に優しいWアプローチ
「じゃあ、一体どうすればいいの?」と思いますよね。大丈夫、私も毎日が試行錯誤です。でも、体の外側からと内側から、両方でできる、とってもシンプルで優しい方法があるんです。一緒にやってみませんか?
アプローチ1:「大丈夫だよ」と伝える、魔法のタッチケア
まず基本は、お腹を冷えないようにすること。特に季節の変わり目は、温かい白湯を飲むなど、体を内側から温める意識が大切です。
その上で、優しいタッチケアを取り入れてみましょう。肌と肌が触れ合うことは、何よりの安心感に繋がります。「愛は動詞」という言葉を大切にしていますが、触れることは、まさに愛情そのものなのです。
- 基本のケア(予防に):
お子さんのお腹を、ひらがなの「の」の字を描くように、時計回りに優しくなでてあげましょう。これは腸の流れに沿ったマッサージ。「気持ちいいね」と声をかけながら、ぜひ試してみてください。 - 便秘がちな時に:
両方の脇腹から、おへそに向かって、手のひらでそーっと撫で寄せるようにします。「早く出ろ〜」と圧力をかけるのはNG!優しく、優しくが基本です。 - お腹がゆるい時に:
足首を両手で包み込むようにして、くるくる〜っと回し撫deてあげましょう。膝から足首にかけてを、上から下にそっと撫で下ろしてあげるのもおすすめです。
アプローチ2:「頑張りすぎない」が合言葉。お腹が喜ぶ、ちりつも食習慣
分子栄養学の視点では、お腹の不調がある時、小麦に含まれる「グルテン」と乳製品に含まれる「カゼイン」が、腸に小さな炎症を刺激してしまう可能性が指摘されています。
【ちあきが先生に聞いてみた!ひとこと解説コーナー】
「でも、アレルギー検査では陰性だったのに…?」
そう思いますよね。私も気になって、夫(小児科医)に聞いてみました。
すると、こんな答えが返ってきました。
「蕁麻疹が出るような『即時型アレルギー』だけが不調の原因じゃないんだ。クリニックでお腹の弱い子を診ていると、もともと腸に何らかの小さな炎症が起きているケースが少なくないんだよ。腸がそういうデリケートな状態だと、普段なら問題ないはずの食べ物にも過敏に反応してしまうことがある。特にグルテンやカゼインは、そうした腸の炎症を刺激しやすい性質があると言われていて、それが数時間後や翌日の『なんだか調子が悪い…』という反応に繋がっているのかもしれないね」
ということでした。
アレルギーという名前はつかなくても、特定の食べ物が、今のあなたの腸にとっては少し負担になっている、というサインなのかもしれませんね。
この小さな負担が続くと、「リーキーガット症候群」という状態に繋がることも。例えるなら、腸という名の「網戸」の目が、少し緩んでしまっているようなイメージです。
だから、いきなり「断捨リ」しなくて大丈夫!
まずは、「いつも頑張っている腸を、少しだけ休ませてあげる」そんな優しい気持ちで、負担になりやすいものを少しお休みしてみませんか? そうすることで、荒れてしまった腸の畑を休ませ、良い腸内細菌が育ちやすい環境(=腸内環境)を整えることに繋がります。
そして腸を休ませながら、元気な畑を育てるために特に意識したいのが、エネルギー作りの主役である「鉄」と「ビタミンB群」です。
ビタミンB群は、食べたものをエネルギーに変えるための「潤滑油」。そして鉄は、そのエネルギーに火をつける「着火ライター」のようなもの。どちらが欠けても、私たちの元気は生まれません。そして何より、弱った腸の粘膜を新しく作り替えるための大切な「材料」にもなるのです。
- 鉄やビタミンB群が豊富な食材:
- かつお、牛肉(赤身)、レバー、あさり など
特にかつおは、鉄分もビタミンB群も両方豊富なスーパースター! 牛肉の赤身も、体に吸収されやすい形の鉄分がたっぷりです。
【はじめの一歩におすすめの一品】
いつものお味噌汁に、あさりを加えたり、かつお節を「これでもか!」と追い鰹してみたり。そんな小さな工夫の「ちりつも」が、きっとお腹の元気につながっていきます。
まとめ|あなたも、私も、失敗しながら成長していく仲間です
「腸は第二の脳」そして「皮膚は、むき出しになった臓器」とも言われます。お腹の調子が私たちの心や肌の状態と深く繋がっていることを、私自身、日々実感しています。
長年の便秘も、息子の頻便も、それは「悪いこと」ではなく、体からの大切な「お知らせ」だったのかもしれません。
完璧な食事やケアなんて、ありません。私も失敗ばかりです。でも、自分の体の声、そして子どもの体の声に耳を澄ませて、「今日はどうかな?」と試してみる。その繰り返しが、私たち親子を一緒に成長させてくれるのだと信じています。
まずはお腹を温めることから。そして、優しい「の」の字マッサージから。
できることから一つ、始めてみませんか?
【より詳しく知りたいあなたへ】
この記事を読んで、「うちの子や私の不調も、もしかしたら…」と、ご心配に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
日々の食事やケアを工夫してもなかなか改善しない、あるいは、一度きちんと体の状態を知っておきたい、という場合は、専門家の力を借りるのも一つの大切な選択肢です。
夫の小森こどもクリニックでは、血液検査を通して、お子さんやご自身の体の栄養状態をより詳しく知ることができます。目に見えない体の内側の状態を客観的に把握することは、悩みの根本的な原因を見つけ、適切なケアを始めるための、確かな一歩になります。
もしご興味がありましたら、ぜひこちらのページも参考にしてみてくださいね。