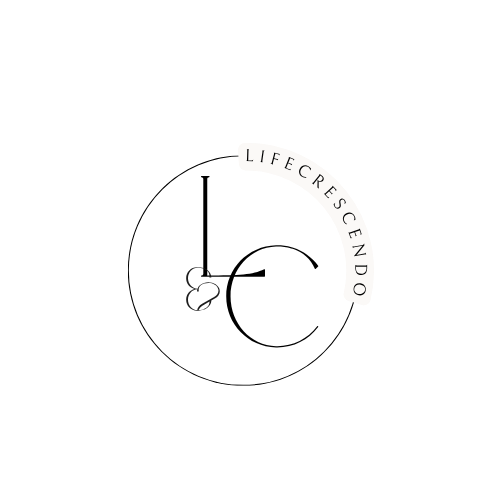LifeCrescendo | 哲学医とライフコーディネーターの探求室
2025年8月9日
哲学医(小森 広嗣):
「あれほど待ち望んだはずの夏休みなのに、どうして…」
蝉時雨のなか、クーラーの効いた部屋で、ただ時間が過ぎていくのを眺めている。部活と塾に明け暮れたあの日々が、まるで遠い昔のことのようだ。身体は休んでいるはずなのに、鉛のように重く、寝ても寝ても疲れがとれない。
親は「どこか悪いんじゃないか」と心配そうな顔をしている。自分でも、この原因不明の倦怠感に「自分は怠けているだけなんじゃないか」と、静かな罪悪感を抱いているかもしれない。
もし、あなたや、あなたの大切な人がそんな状況にいるとしたら。
まず、心に留めておいてほしいことがあります。それは、病気でも、怠けでもありません。むしろ、これまであなたが、いかに真面目に、誠実に、目の前のことに向き合ってきたか、という「証」なのです。
これは、頑張り屋さんほど陥りやすい、「休息のワナ」とでも言うべき、心と身体の正直な反応。この記事では、そのメカニズムを哲学的な視点と、私たちの脳の中で起きている科学的な事実の両面から紐解き、あなたが本来のエネルギーを取り戻すための、思考の処方箋をお渡しします。
診察室の風景:ある中学生の、正直な物語
先日、中学3年生の男の子が、お母さんと一緒に私のクリニックを訪れました。主訴は、5日前から続く「原因不明の倦怠感」。
話を聞くと、彼の7月までの日常は、目まぐるしいものでした。
週に3〜5回、午前中は部活の練習に汗を流し、午後は塾へ向かう。そんな、心身ともに活動的な毎日が、彼の「当たり前」だったのです。
しかし、8月に入り、部活も塾も、ぱったりと休みになりました。
その数日後から、彼の身体は悲鳴を上げ始めます。「寝ても疲れがとれない」「身体がだるくて動けない」。
お母さんは、何か大きな病気が隠れているのではないかと、ひどく心配されていました。しかし、診察をしても、器質的な疾患を示唆する所見は見当たりません。
彼の身体に起きていたこと。それは、病気ではなく、「生活スタイルの急変に伴う、自律神経の不協和音」でした。
哲学医の診断:なぜ「休む」とかえって疲れるのか?【脳と身体のメカニズム】
私たちは「疲れたら休む」ことを、絶対的な正解だと信じています。しかし、物事には常に「程度」と「バランス」が存在します。
彼のケースは、「高速で回転していたコマを、急に無理やり止めた」ような状態でした。私たちの身体は、その急激すぎる変化を「ストレス」として認識し、ストレスホルモンである「コルチゾール」を過剰に分泌し始めます。いわば、身体が一日中、微弱な「非常警報」を鳴らし続けている状態。これが、寝ても取れない倦怠感や無気力感の、科学的な正体の一つです。
同時に、彼の充実した日常は、脳にとって「3つのご褒美」が安定供給される、最高の環境だったのです。
- 心の安定剤「セロトニン」:規則正しい生活リズムと適度な運動が生み出す、穏やかな心の素。
- やる気の源「ドーパミン」:練習や勉強での小さな「できた!」が与えてくれる、達成感という名の報酬。
- 天然の活力剤「エンドルフィン」:運動後の爽快感や高揚感。
「完全な休息」とは、この3つの重要なご褒美が、脳から突然取り上げられてしまった状態でもあります。これでは、心が元気をなくしてしまうのも、無理はありません。
これは、私たちが大切にする「農場の法則」にも通じます。毎日、決まった時間に水や太陽(ご褒美)を与えられていた作物が、その営みを断たれたらどうなるか。私たちの身体と脳もまた、これまで積み重ねてきた「健やかなリズム」という名の恵みを求めているのです。
本当のエネルギーは、「使う」ことで生まれる
ここで、多くの人が誤解している、エネルギーに関する重要な真実をお伝えしなければなりません。
私たちは、エネルギーを「スマートフォンのバッテリー」のように考えがちです。使えば減るから、使わないで充電(休息)しなくては、と。
しかし、人間のエネルギーは、それほど単純ではありません。ブランド哲学の根底にある「エネルギー創造の法則」が示すように、エネルギーは消費するだけのものではなく、意志と行動によって「創造」できるものなのです。
つまり、適度に活動し、身体を使うこと自体が、次のエネルギーを生み出す「種火」となる。
元々活発な人にとって、「何もしないこと」は充電どころか、エネルギーを生み出すエンジンそのものを止めてしまう行為になりかねません。だからこそ、休んでいるはずなのに、かえって疲れてしまう、というパラドックスが生まれるのです。
結論:人生は「バランス」という名の中庸を探す旅
では、どうすればいいのか。
答えは、驚くほどシンプルです。
「ゼロか、百か」という思考を手放すこと。
「全力で活動する」か、「全く何もしない」か。私たちは、無意識にこの両極端な選択肢に囚われがちです。しかし、本当に大切なのは、その中間に広がる、あなただけの「心地よい活動レベル」を見つけ出すことです。
古代ギリシャの哲学者アリストテレスが説いた「中庸(ちゅうよう)」という概念があります。それは、過不足のない、調和のとれた状態こそが、最高の「善」であるとする考え方です。
あなたの身体が求めているのも、まさにこの「中庸」。
全力疾走でもなく、完全停止でもない。心地よいペースでのジョギングのような、穏やかで、持続可能な活動のリズムです。
この「バランス」を探す視点は、夏休みの過ごし方だけでなく、仕事、勉強、人間関係、そして人生のあらゆる局面において、あなたを支える揺ぎないコンパスとなるでしょう。
今日の、人生の処方箋
最後に、この「休息のワナ」から抜け出し、再び健やかなエネルギーの流れを取り戻すための、具体的な3つのステップを処方します。これは、あなたの脳を安心させ、再び「幸福ホルモン」という名の恵みで満たすための、具体的なアクションです。
- その倦怠感を、「頑張りの勲章」だと認める。
まず、「自分は怠けている」という自己批判を手放してください。その不調は、あなたの脳と身体が、急な変化に戸惑っている正直なサイン。あなたがこれまで真剣に物事に取り組んできた何よりの証拠です。 - 脳を安心させる「ミニチュア版」のリズムを試す。
止まってしまったセロトニンやエンドルフィンのエンジンを、優しく再点火してあげましょう。部活に行っていた午前中に、20分だけ散歩をする。それだけで、脳は「いつものリズムが戻ってきた」と安心し、過剰なコルチゾールの分泌を抑えてくれます。 - 小さな「できた!」で、やる気の種火を灯す。
ドーパミンは、大きな目標でなくても構いません。「午前中に10ページだけ本を読む」といった、ごく小さな目標を立て、達成する。その「できた!」という感覚が、枯渇していたやる気の泉に、再び水を満たし始めます。
あなたのその“灰色”の時間は、決して、無駄なものではありません。むしろ、それこそが、人生における「変化とのしなやかな付き合い方」を、心と、身体と、そして脳で学ぶための、最高のレッスンなのですから。
あなたの「ヒビ割れ」が、最高の輝きに変わる日を、心から信じています。