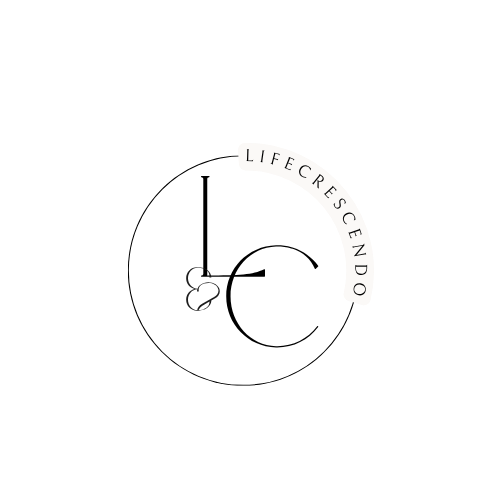こんにちは!
LifeCrescendoのライフコーディネーター、3人の子育て真っ最中のちあきです。
「お母さーん、お腹すいたー!」が無限に続くエンドレスわんこそば状態(笑)。
冷蔵庫を開ければ、昨日補充したはずの麦茶は空っぽ、お菓子の空き箱が虚しく転がっている…。
そんな夏休みの光景に、思わず天を仰いでしまったのは、きっと私だけではないはずです。
わが家もご多分に漏れず、ついタブレットの力に頼ってしまう時間が増え、気づけばその”魔法の画面”なしでは一日が回らないような、そんなスパイラルにはまっていました。
特に私の心を曇らせていたのが、エネルギーあふれる次男のこと。
夏休みに入ってから、なんだか拍車をかけて落ち着きがなく、まるで小さな怪獣のように家の中を駆け回り、ちょっとしたことで大爆発。
「これはきっと、タブレットの見すぎが原因だわ!」
そう信じて、心を鬼にしてタブレットを没収したんです。でも…あれ?期待していたほど、息子の様子は変わらない。むしろ、棒を振り回す勢いは増しているような…。
「どうして…?私の愛情が足りないのかな」「もっと根気よく向き合うべきなの?」
そんな答えのない問いが、ぐるぐると頭の中を巡っていました。
「それ、性格じゃなくて”ガス欠”かもよ?」
きっかけは、小児科医であり、わが家の父親でもある夫からの、ふとした一言でした。
「最近の次男の様子、もしかしたらエネルギー源になるタンパク質と鉄が足りていない、ただの”ガス欠”状態なのかもよ」
え、栄養…?ガス欠…?
「でも、うちはご飯をしっかり食べてるつもりだけど…?」と、すぐにはピンと来ませんでした。
すると夫は、私にとって目から鱗が落ちるような話をしてくれたのです。
実は、たとえお腹いっぱい食べていても、体の中が本当に必要な栄養で満たされているとは限らない。そんな「隠れ栄養失調」という状態があるそうなのです。
私たち現代の食生活って、どうしても手軽なパンやお米、麺類といった炭水化物中心になりがちですよね。もちろん炭水化物は大切なエネルギー源なのですが、そればかりに偏ってしまうと、血糖値がジェットコースターのように乱高下してイライラの原因になったり、そもそも体の中でエネルギーを効率よく作り出すために不可欠なビタミンやミネラル(鉄、亜鉛、マグネシウムなど)が、実は全然足りていなかったりするんだとか。
「どんなに良い車でも、ガソリンだけじゃなくて、エンジンオイルや冷却水がないとスムーズに走れないでしょ?体も同じで、炭水化物という”ガソリン”だけじゃなく、ビタミンやミネラル、タンパク質という”潤滑油”や”ボディの材料”があって初めて、心も体も安定して動けるんだよ」
夫からそう聞いて、ハッとしました。
あの癇癪が、性格や育て方の問題ではなく、ただ体の中でエネルギーがうまく作れずに起こる”機能不全”のサインだったなんて、考えたこともありませんでした。
でも、藁にもすがる思いで、半信半疑のまま、わが家の食生活をちょっとだけ見直してみることにしたんです。
わが家で始めた「ちょい足し」大作戦!
やったことは、本当にシンプルです。
「完璧な栄養満点の食事を作る!」なんて意気込むと続かないので(笑)、いつもの食事に、ほんの少しだけタンパク質を意識した食材をプラスしてみただけなんです。
- いつものおやつにプラス!: 食パンにジャム、も美味しいけれど、サラダチキンやナッツをかじってみる日を作る。
- いつもの食卓にプラス!: 鶏のささみ肉を使ったメニューを増やしたり、朝からお魚の代わりにお肉を出してみたり。
無理のない範囲で、まさに「ちりつも」の精神です。
私自身も、仕事の合間に急いで食べていたおにぎり一個の昼食に、コンビニで買えるサラダチキンや大豆バーをプラスするようになりました。
正直、「こんなことで、本当に何かが変わるのかな?」と思っていました。でも、変化はすぐに、そして私が一番驚くような形で現れたのです。
小さな怪獣が、穏やかな探求者に!?
この「ちょい足し大作戦」を始めて数日後のこと。
あれだけ家の中で大暴れしていた次男が、なんだかニコニコと穏やかに過ごしている時間が増えたことに気づきました。
そして、極めつけは、ある日の午後。
私が何も言っていないのに、自分からスッと机に向かい、なんと1時間半も集中して漢字の勉強をしていたのです!翌朝も、起きてきたらまず勉強。
「……あなた、本当にあの次男くんですよね?」
あまりの変化に、嬉しいというより、あっけにとられてしまいました。
私自身も、夕方になると感じていた、あの、どーんっと重たい疲れがふっと軽くなり、一日中元気に笑顔でいられる時間が増えていることに気づきました。「食べるものが変わると、世界はこんなにも違って見えるんだ!」と、身をもって体感した瞬間でした。
心の土台は、「体」が作っていた
この経験を通して、私はとても大切なことを、改めて教えられました。
それは、「心も、体の一部なんだ」ということです。
私たちはつい、子どもの癇癪や自分のイライラを、「性格」や「心の持ちよう」の問題だと捉えがちです。でも、その心の状態を支えているのは、間違いなく「体」という土台なんですよね。
畑の野菜が、水や太陽の光、そして土の栄養がなければ元気に育たないのと同じように(農場の法則)、私たちの心も、体に必要な栄養が行き届いて初めて、穏やかに、健やかに花開くのかもしれません。
実はこのアプローチの背景には、「分子栄養学」という、しっかりとした学問的な裏付けがあるそうです。
なんだか名前だけ聞くと、少し難しそうに感じますよね。
そんな時、夫はよく、私たちの体を「オーケストラ」に例えてくれます。
タンパク質やビタミン、ミネラルといったたくさんの栄養素は、それぞれがバイオリンやピアノ、トランペットのような大切な「楽器」なんだ、と。
どれか一つの楽器の音がずれていたり、欠けていたりすると、美しいシンフォニー(=心と体の健康)は奏でられません。炭水化物に偏った食事は、まるでピアノだけが大音量で鳴り響いているような状態なのかもしれませんね。
分子栄養学というのは、このオーケストラ全体を見渡し、食べたものをエネルギーに変えるための『潤滑油』(ビタミン・ミネラル)や、体そのものを作る『材料』(タンパク質、脂肪)といった全ての楽器が、最高の音色を奏られるように調律(チューニング)していく、という考え方なんですね。
まとめ|あなたは、もう、じゅうぶん頑張っています
もし今、この記事を読んでくださっているあなたが、お子さんのことで悩んでいて、「私の育て方が悪いのかも…」なんて自分を責めてしまっているとしたら、どうか、その手を止めて深呼吸してみてください。
あなたは、もう、じゅうぶん頑張っています。
その悩みは、あなたの愛情が足りないからでは決してありません。ただ、心と体のエネルギーが、少しだけアンバランスになっているサインかもしれないのです。
完璧な食事を目指さなくても大丈夫。
いつものおやつを、ちょっとだけ変えてみる。そんな「ちりつも」の一歩が、あなたとあなたの大切な家族の毎日を、もっと笑顔にしてくれるかもしれません。
私もまだまだ学びの途中です。失敗しては学び、学んではまた失敗する、その繰り返しです。でも、それでいいんですよね。
昨日よりほんの少し、子どもと自分の笑顔が増えること。そんな「ちりつも」の幸せを、あなたと一緒に見つけていけたら、こんなに嬉しいことはありません。
追伸
わが家の場合は「ちょい足し」から始めることができましたが、「もっと具体的に、うちの子に合った方法が知りたい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ちなみに、小森こどもクリニックでは、血液検査でお子さん一人ひとりの栄養状態を詳しくお調べし、その結果をもとに最適な食事の工夫やサプリメントをご提案することも行っています。
専門家の視点が必要だと感じた時は、頼れる場所があることも、心の片隅に置いておいていただけたら嬉しいです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。